社会福祉法人の「社会福祉充実残額」とは?制度の基本を解説
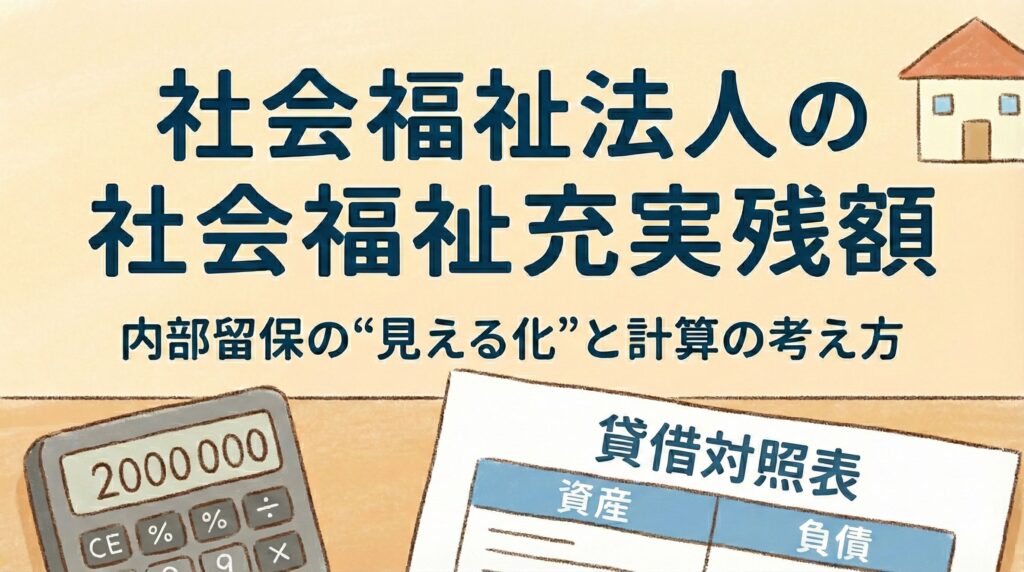
社会福祉充実残額とは何か?この記事では、制度の目的から計算の考え方、社会福祉充実計画の策定まで、社会福祉法人の理事・評議員・施設長・事務長・経理担当者の方向けにわかりやすく解説します。
本記事は、公開されている法令・通知等にもとづき一般的な考え方を整理したものです。個別の判断にあたっては、必ず所轄庁や専門家にご相談ください。また、所轄庁がガイドラインや様式集を公開している場合も多いため、あわせてご確認ください。
Contents
1. 「社会福祉充実残額」—“内部留保の見える化”ルールです
社会福祉充実残額は、平成28年の社会福祉法改正(第55条の2)で導入された、比較的新しい会計上の仕組みです。
すべての社会福祉法人に、毎会計年度、次の2点が求められています。
- 「社会福祉充実残額」の計算: 法人が持つ財産のうち、事業を続けるために必要な分を差し引いた「再投下できる余力」がいくらかを計算する。
- 「社会福祉充実計画」の策定と承認: もし残額(余力)が生じた場合、原則としてその使い道を示した計画書を作成し、所轄庁の承認を得る。
この制度ができた背景には、「社会福祉法人は内部留保を貯め込み過ぎでは?」という世間の厳しい目や、公的な財源で成り立つ法人としての説明責任があります。
とはいえ、将来の建替えや運転資金など、事業継続のための内部留保が不可欠なのも事実です。
そこで、この制度は「必要な蓄え」と「地域や福祉サービス向上のために使える余力」を客観的に切り分け、見える化するためのルールと理解するとよいでしょう。
この記事では、法人の役員・施設長・実務担当者向けに、社会福祉充実残額の全体像をスムーズに把握できるよう、以下の3つのポイントに絞って解説します。
- 社会福祉充実残額とは、結局どんなお金か?
- どんな流れで計算するのか?(3ステップで理解する計算の考え方)
- 残額が出たら、何をすべきか?(社会福祉充実計画のポイント)
2. 社会福祉充実残額とは、「自由に使える余力」のこと
まずは、ざっくりとしたイメージを掴みましょう。
社会福祉充実残額とは
事業継続のために最低限必要な財産を確保したうえで、
これから福祉サービスの充実や地域のために使える“余力”の金額
と理解するのが最もシンプルです。
重要なのは、法人が持つ内部留保のすべてが対象ではない、という点です。
この制度は、次のような前向きな整理を促すための仕組みと捉えましょう。
- まず、事業継続に必要な財産(建物・設備・将来の建替え費用・運転資金など)は、きちんと確保する。
- そのうえで残った“余力”の部分を、計画的に福祉サービスへ再投下する。
3. 社会福祉充実残額の計算の考え方:3ステップで「余力」を算出
実際の計算は、厚生労働省が公表するExcelの算定シートで行いますが、ここでは計算の「考え方」を3つのステップで解説します。
ステップ1:財産の“全体像”を把握する(活用可能な財産)
まず、法人全体の貸借対照表をもとに、自由に活用できる可能性のある財産がどれだけあるかを把握します。
「活用可能な財産」の計算
活用可能な財産 = 資産 - 負債 - 基本金 - 国庫補助金等特別積立金
これは、ざっくり言えば「これまでに法人に蓄積された内部留保のうち、補助金など使い道が固定されているものを除いた部分」とイメージすると分かりやすいでしょう。
具体的には、貸借対照表の純資産から「基本金」と「国庫補助金等特別積立金」を引いた部分が、「活用可能な財産」にあたります。
この段階でマイナスやゼロなら、その年度の社会福祉充実残額は生じません。以降の計算は不要です。
ステップ2:事業継続に「不可欠な財産」を差し引く(控除対象財産)
次に、ステップ1で把握した財産から、「事業を続けるために、これだけは手元に残しておく必要がある」という最低限の財産を見積もって差し引きます。
この「不可欠な財産」は、大きく次の3種類です。
- 現在の事業に使っている土地・建物など
- 特養・保育所など、社会福祉事業の実施に不可欠な不動産・設備等
- 将来の建替え・大規模修繕・設備更新に必要な分
- 建物の老朽化を見据えた建替え費用
- 大規模修繕、設備・車両の更新に必要な資金
- 運転資金(当面の支払いに必要な現金預金など)
- 人件費や事業費の支払いのための現金預金など
- 年間の事業活動支出の3カ月分が認められています
これらを合計したものが「控除対象財産」となります。
具体的な金額の出し方は通知やQ&Aで細かく定められており、実務上は厚労省の算定シートに沿って、ある程度機械的に計算することとなります。
なお、2. 将来の建替え費用と3. 運転資金3ヶ月分の合計額が、法人全体の年間事業活動支出を下回るような場合には、2. 3. の代わりに年間事業活動支出を控除対象とする特例的な計算方法も認められています(いわゆる「運転資金1年分」の特例)。
控除対象財産の計算にあたっては、
- どの施設・設備を建替えや更新の対象とするのか
- 建替えや整備の優先順位をどう考えるのか
といった前提や考え方を、理事会・評議員会で共有しておくと、後から説明しやすくなります。
ステップ3:差額が「社会福祉充実残額」となる
最後に、ステップ1と2の結果を引き算します。
「社会福祉充実残額」の計算
社会福祉充実残額 =活用可能な財産(ステップ1) -控除対象財産(ステップ2)
- この差額が0円以下なら、その年度の社会福祉充実残額は「なし」です(計画策定も不要)。
- 差額がプラスになった場合、その金額が社会福祉充実残額となり、原則として次のステップである「社会福祉充実計画」の策定に進みます。
4. 社会福祉充実残額が出たら?「社会福祉充実計画」で使い道を示す
社会福祉充実残額にプラスが生じた場合、原則として、法人は「社会福祉充実計画」を作成し、所轄庁の承認を得る必要があります。これは、算出した“余力”を、どのように地域や福祉サービス向上のために活用するかを約束する計画書です。
4-1. 計画で定める「使い道」
計画には、主に次の内容を記載します。
- 社会福祉充実残額の金額
- どの事業に、いくらを、いつ使うかという資金計画
- 事業の内容(例:職員の処遇改善、人材育成、新たな福祉サービスの開始、施設の増改築、地域貢献活動など)
- 計画の実施期間(原則5年以内)
なお、残額の使い道は、下記の優先順位で検討することが求められています。
- 社会福祉事業の充実(既存事業の拡充など)
- 地域公益事業(地域住民の課題解決に貢献する事業)
- 公益事業(上記1、2以外のもの)
4-2. 手続きの流れと期限
手続きの主な流れは以下の通りです。
- 提出期限: 決算が確定し、社会福祉充実残額を算定した後、原則として会計年度終了後3カ月以内に、計算書類等とあわせて所轄庁へ提出(申請)します。
- 計画策定のプロセス: 計画は、法令で定められた次のプロセスを経て策定する必要があります。
- 公認会計士・税理士等の専門家から、手続きや計画内容について意見を聴く。
- 理事会・評議員会で十分に審議し、承認を得る。
詳細な様式や手続きは、所轄庁の案内に従ってください。
5. よくある誤解とつまずきポイント
この制度に対応する中で、多くの法人がつまずきやすいポイントや誤解をまとめました。
誤解1:「内部留保は“悪”だから、ゼロにすべき」ではない
この制度は、「内部留保をすべて使い切れ」と強制するものでは決してありません。
将来の施設更新や不測の事態に備えるための最低限必要な内部留保は、むしろ計画的に確保すべき、というのが大前提です。そのうえで、「余力があるなら、有効活用する計画を立てましょう」と促す、ポジティブな仕組みと捉えることが大切です。
誤解2:「算定シートの提出=ゴール」と思い込んでしまう
算定シートに数字を入れて所轄庁に提出することは、社会福祉充実残額の制度上、必須の手続きです。
一方で、現場では、「決算が終わったら、とにかくシートを埋めて出す。提出できれば今年の仕事は完了」という感覚になりがちです。
確かに、制度上の義務はそれで果たせています。しかし、「提出=ゴール」になってしまうと、本来この仕組みが持つ経営ツールとしての価値が十分に活かされません。
- なぜ今年は残額が出たのか/出なかったのか
- どの施設・整備計画が、どの程度控除の金額に効いているのか
- 来年度以降、どのような投資や処遇改善に回せそうなのか
といった点を一度振り返ってみることで、同じ算定結果でも「数字の背景」が見えてきます。
誤解3:社会福祉充実残額が「出ない=安心」とは限らない
現場では、算定の結果がゼロやマイナスになると、「残額が出なかったから、社会福祉充実計画を作らなくてよくて助かった」という受け止め方になりがちです。
事務的にはそれで間違いありません。しかし、「残額が出ない=何も問題がない」「安心してよい」と短絡的に考えてしまうのは少し危うい面もあります。
社会福祉充実残額がゼロ・マイナスになる理由として、たとえば次のようなパターンが考えられます。
- そもそも活用可能な財産そのものが小さい(内部留保が薄い)
- 控除対象財産が大きい(とくに、将来の建替え・修繕・設備更新費用を厚めに見込んでいる)
- 年間事業活動支出1年分を控除できる特例を適用している
これらは必ずしも「悪いこと」ではありません。
規模が小さい法人や、これから大きな整備を予定している法人では、現時点では「余力を出さない(出せない)」のが自然な姿ということもあります。
ただし、同じ「ゼロ・マイナス」でも、
- 将来の投資に向けて必要な資金をしっかり確保している結果としてそうなっているのか
- 単に内部留保が少なく、そもそも次の一手に回せる原資が足りていないのか
では、意味合いがまったく違います。
大事なのは、「なぜ当法人では残額が出ていないのか」を一度立ち止まって確認してみることです。
具体的には、次のような観点で眺めてみると、数字の意味合いが見えてきます。
- 活用可能な財産の水準は、経営規模や将来の整備計画と比べてどうか(人件費や支出の何か月分くらいか)
- 控除対象財産の見積もりは、中長期の整備計画やこれまでの修繕実績と整合しているか
こうした点を確認したうえでゼロ・マイナスなのであれば、「今の時点では、次の大きな投資に回せる余力はあまりない状態」と受け止めることができますし、逆に数字だけを見て「残額が出ないから安心」と思い込んでしまうのは避けたいところです。
6. 社会福祉充実残額を経営判断にどう活かすか
社会福祉充実残額の算定は、単なる義務的な事務作業ではありません。見方を変えれば、法人の未来をデザインするための強力な経営ツールになります。
6-1. 主な活用場面
- 戦略的な設備投資の判断軸に
- 「建替えや大規模修繕に、自己資金をいくら投下できるか?」
- 「複数施設のうち、どこから投資を始めるべきか?」
といった意思決定の客観的な根拠となります。
- 職員の処遇改善の原資の把握に
- 処遇改善加算とは別に、法人独自の財源でどの程度の上乗せが可能か、その持続性はどうか、といったシミュレーションが可能になります。
- 地域貢献を具体化する第一歩に
- 「地域のために何かしたい」という思いを、「どのくらいの規模なら無理なく実現できるか」という具体的な計画に落とし込む際の基礎資料になります。
毎年の算定結果をファイルに綴じて終わりにするのではなく、理事会や評議員会で「今後5~10年の法人の姿」を話し合うための共通言語として活用することで、会計情報を、過去の結果を確認するためだけのものから、今後の設備投資や職員処遇、地域貢献の方針を検討するための具体的な材料へと変えていくことができます。
6-2. 社会福祉充実残額がマイナスとなった/大きく変動した年の「読み解き方」
算定シートの結果がゼロやマイナスであれば、社会福祉充実計画の提出は不要になります。
事務的にはそれで完結なのですが、経営の視点からは、少なくとも一度は「なぜそうなっているか」を確認しておくことをおすすめします。
たとえば、次のような整理の仕方があります。
- 毎年ゼロ・マイナスが続いている場合
- 活用可能な財産(内部留保)の水準は、この数年で増えているのか、横ばいなのか、減っているのか
- 控除対象財産の前提(整備計画・修繕費の見込み・運転資金)が、数年前と比べてどう変わっているのか
- ある年度だけ急にゼロ・マイナスになった場合
- 大きな設備投資や建替えなど、一時的な要因が影響していないか
- 特例計算を用いたことにより、控除額が一気に増えたのか(特例計算を用いなかった場合、本質的な活用可能な財産はどの程度なのか)
逆に、急に大きなプラスが出た年も要注意です。
- 一時的な要因(大きな補助金、資産売却など)で増えていないか
- もともと予定していた整備が先送りになっていないか
などを確認することで、
- 今は一時的に余力が大きく見えているだけか
- 継続的に投資や処遇改善に回せる力がついてきているのか
を見分けるヒントになります。
忙しい現場で、毎年そこまで細かく分析するのは現実的ではないかもしれません。
それでも、大きく数字が動いた年度や、将来の整備を本格的に検討するタイミングだけでも、算定結果の背景を経営陣で共有しておくと、後々の判断がしやすくなります。
7. まとめ
本記事では、社会福祉充実残額の考え方から実務上のポイントまで、全体像を解説しました。
- 社会福祉充実残額とは、事業継続に必要な財産を差し引いた「再投下できる余力」である。
- 社会福祉充実残額は、「活用可能な財産の算定 → 控除対象財産の算定 → 差額の算出」という3ステップで計算される。
- 社会福祉充実残額が生じた場合は「社会福祉充実計画」を策定し、職員の処遇改善や地域貢献などに活用する。
- 社会福祉充実残額の制度の本来の目的は、計算そのものではなく、法人の財産状況を“見える化”し、将来の経営を議論する材料とすること。
この制度を、単なる義務としてこなすだけでは非常にもったいないと言えます。
まずは決算後に算出した残額について、「なぜこの数字になったのか」を経営陣で共有することから、法人の持続的な発展のための経営ツールとして活用していきましょう。
8. 参考情報
制度の詳細や最新の取扱いについては、以下の公的資料をご確認ください。
- 厚生労働省「社会福祉充実計画」:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13288.html - 厚生労働省「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.3)」:
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000191933.pdf - e-Gov法令検索「社会福祉法(第55条の2を含む)」:
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000045
9. 当事務所で支援できるサービス
当事務所では、社会福祉法人のお客様向けに、次のようなサポートを行うことができます。お気軽にご相談ください。
- 厚労省算定シートを用いた社会福祉充実残額の試算・シミュレーション
- 将来の建替え・修繕・設備更新計画と連動した「控除対象財産」の整理支援
- 特例計算(年間事業活動支出1年分)の適用可否や影響の整理
- 社会福祉充実計画(案)の作成支援
- 理事会・評議員会・管理職向けの説明資料作成・研修
10. 関連内部リンク
💬 Threads(@daichi_tax)で「税と会計の小さな気づき」を短文で発信しています。
👉 https://www.threads.net/@daichi_tax
📘 noteでは読みやすい”3分要約記事”を更新中です。
👉 https://note.com/daichitax





