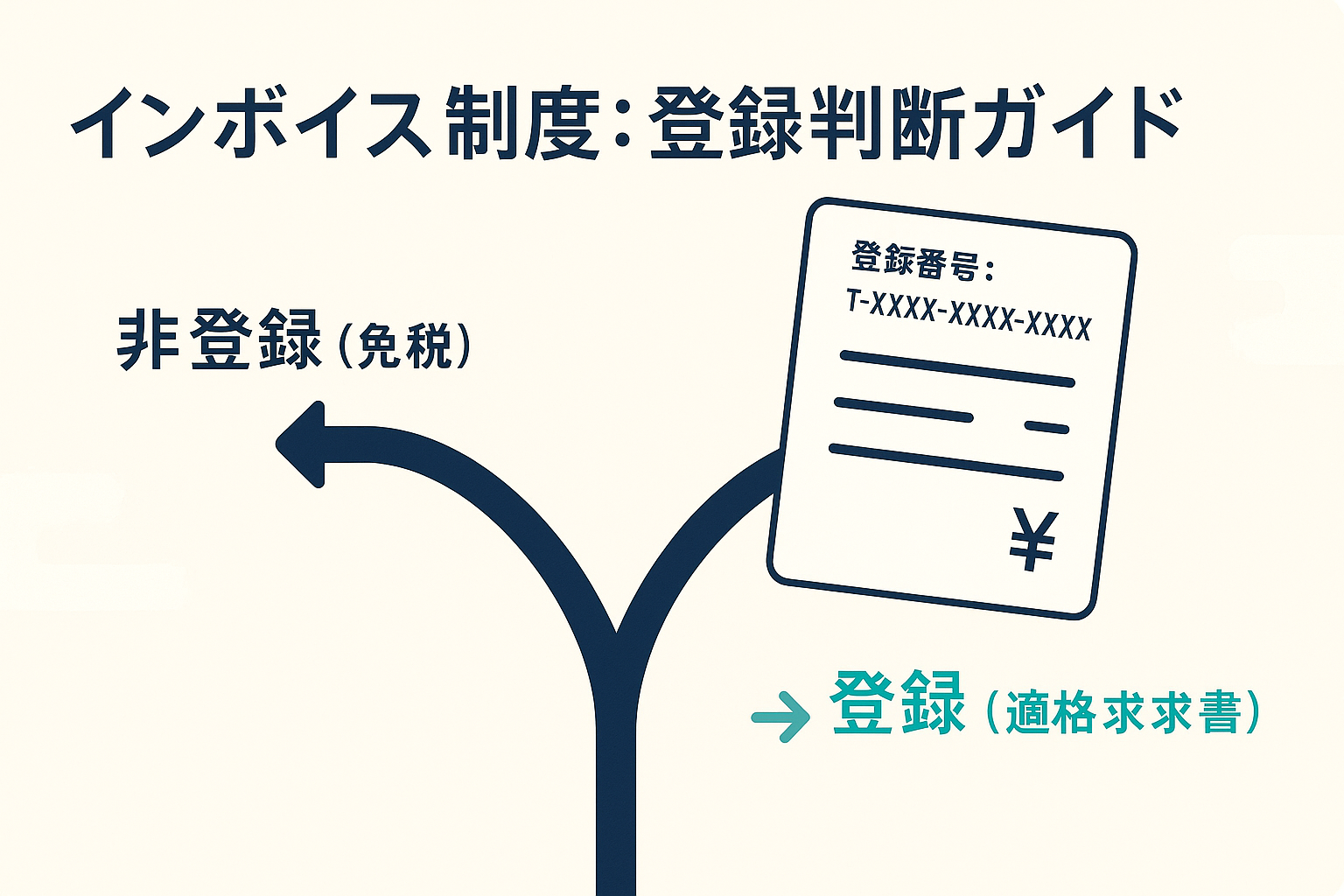消費税「簡易課税」の選び方。業種区分・みなし仕入率と2割特例を比較解説

簡易課税を選ぶべきか?簡易課税の業種区分(みなし仕入率)や75%特例 、2割特例との有利不利を比較。基準期間5,000万円以下 の方へ、制度選択の判断フローと計算事例を解説します。はじめての方でも制度の選び方のポイントがわかります。
本記事は、一般的な概要と選択肢について解説するものです。特定の個人・法人に対する税務アドバイスを提供するものではありません。制度の適用や具体的な税務判断にあたっては、必ず最新の法令等をご確認いただくか、税理士等の専門家または所轄税務署にご相談ください。
▶短時間で確認したい方はこちら:note版(無料)
Contents
消費税 簡易課税の選び方(結論)
- 誰に向くか:実態の仕入率(=実際の課税仕入の割合の概算)よりも、みなし仕入率の方が大きい事業者。前提は基準期間の課税売上高5,000万円以下+事前の届出。
- みなし仕入率:事業区分は取引ごとに判定。複数業種は75%特例を活用可(有利選択)、事業区分未区分は最低40%で不利。
- 他制度との関係:2割特例は2026年9月30日の属する課税期間まで。要件を満たす場合、各期で申告時に「2割特例」による選択可。設備投資・還付が絡む期は専門家への相談を推奨。
この記事の想定読者/到達目標
- 想定読者
- 国内事業者であるフリーランスや小規模法人(概ね売上5,000万円以下)を想定し、当期に多額の設備投資や還付申告の予定がない方
- 簡易課税制度の一般的な内容を学びたい方
- 到達目標
- 自分(自社)が簡易課税を選ぶべきか、どの事業区分・みなし仕入率を使うか、2割特例との優先順位まで判断できる
重要
本記事は上記の想定読者向けに消費税の簡易課税制度についての一般論を整理したものです。調整対象固定資産の取得や高額特定資産の取得をした場合、複数年にわたる有利・不利判定などを判断するような場合は、本記事の内容は当てはまらない可能性があります。このような事例に該当し個別の税務判断が必要となる場合には、専門家または所轄税務署に相談することをお勧めします。
1. 消費税の簡易課税制度の概要
1-1. 消費税の計算方式の全体像
消費税の計算は「原則課税」と「簡易課税」の二方式があります。加えて、インボイス登録を契機に免税→課税となった小規模事業者向けの「2割特例」(時限措置)があります。
「原則課税」は売上税額と仕入税額を請求書・帳簿に基づき実額で計算する方法です。
「簡易課税」は売上税額は実額で計算し、仕入税額の計算は売上税額を元に概算で計算する方法です。
「2割特例」は、仕入税額の実額控除を行わず、当該課税期間の売上税額の20%を納付税額とする簡便な方法です。
- 原則課税:納付税額=売上税額-仕入税額(実額)
- 簡易課税:納付税額=売上税額-仕入税額(売上税額×みなし仕入率)
- 2割特例:納付税額=売上税額×20%
原則課税と簡易課税の違い
- 原則課税は売上税額<仕入税額となる場合は払いすぎた税額が還付される。
- 簡易課税は仕入税額を売上税額を元に概算で計算するため、売上税額<仕入税額となることはない。(中間納付還付を除き、還付されることはない)
- 原則課税・簡易課税どちらが有利になるかは状況による。
1-2. 消費税の計算方式の比較(一般論)
計算方式 | 主な適用条件 | メリット | 留意点 | 向き | 不向き |
|---|---|---|---|---|---|
原則課税 | 原則の計算方法 | 売上税額<仕入税額となる場合は還付 | 税区分の判定・証憑保存等の事務負担 | 設備投資期/仕入税額が多い | 記帳体制が未整備/事務の簡便さを優先したい |
簡易課税 | 基準期間の課税売上高5,000万円以下+届出 | 原則課税に比べ事務負担が軽い/見込みが立てやすい | 控除不足還付の概念なし/原則2年間は強制適用 | 実態の仕入率<みなし仕入率となりがち/事務負担を軽減したい | 実態の仕入率>みなし仕入率となりがち/大規模投資の予定がある |
2割特例 | インボイス登録(免税→課税該当)+基準期間の課税売上高1,000万円以下等 | 原則課税に比べ記帳負担が軽い/見込みが立てやすい/納税額が一番有利になりやすい | 期間限定/簡易と併用不可(申告上いずれかを選択) | 実態の仕入率又は簡易課税のみなし仕入率<売上税額の2割となる/事務負担を軽減したい | 簡易課税・原則課税の方が納税額が少なくなる場合 |
2割特例
- 2割特例を適用できる期間は2026年9月30日までの日の属する各課税期間までです。
- 2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。
1-3. 簡易課税制度の概要
簡易課税制度とは、売上税額に業種ごとに定められたみなし仕入率(2-2.業種別のみなし仕入率の表を参照)を乗じて控除対象仕入税額を算出する簡便的な計算方法です。仕入税額の集計をしなくて済むため、事務負担が軽減されます。
簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、原則として課税期間開始日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が選択できます(簡易課税制度をやめる場合も前日まで)。簡易課税制度を選択した場合、適用開始から原則2年間は簡易課税による計算が強制適用となります。
1-4. 簡易課税制度の適用要件
- 対象者:課税事業者であること(免税事業者は「課税事業者選択届出書」により課税事業者となる場合を含む)。
- 規模要件:基準期間の課税売上高が5,000万円以下。※基準期間がない場合はこの判定は不要。
- 届出書の提出:適用しようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署へ提出(書面/e-Tax)。
選択しようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間等である場合は、その課税期間中の提出で当該課税期間から簡易課税を適用可能。
【参考:国税庁HP D1-22 消費税簡易課税制度選択届出手続】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm - 注意点:
- 簡易課税制度の選択後は原則2年間は強制適用。
- やめる場合は「簡易課税制度選択不適用届出書」を適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出。(簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書は提出不可。)
- 原則課税により計算した課税期間中に、調整対象固定資産(建物・機械等で税抜100万円以上)の取得や高額特定資産(1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産)の取得があるような場合は、簡易課税制度の適用に制限が生じる場合があります。このような場合は、本記事の記載内容が当てはまらない場合があります。個別の税務判断が必要な場合は専門家に相談することをお勧めします。
2. 簡易課税制度による計算の概要
2-1. 簡易課税制度による消費税の計算式
- 簡易課税制度による消費税の納付税額=売上税額−控除対象仕入税額
- 売上税額=税抜売上×税率(標準税率・軽減税率ごとに計算)
- 控除対象仕入税額=売上税額×みなし仕入率(以下の表を参照)
2-2. 業種別のみなし仕入率
簡易課税制度は、事業形態により、第1種から第6種までの6つの事業に区分し、それぞれの事業の課税売上高に対し各事業に対応するみなし仕入率を乗じて仕入控除税額を計算します。
種類 | みなし仕入率 | 業種 |
|---|---|---|
第1種 | 90% | 卸売 |
第2種 | 80% | 小売 |
第3種 | 70% | 製造・建設等 |
第4種 | 60% | 飲食店業等 |
第5種 | 50% | 運輸通信・金融保険・サービス(飲食店除く) |
第6種 | 40% | 不動産 |
- 種類の判定は取引単位(課税資産の譲渡等ごと)で行うことが原則です。
- 【参考:国税庁 タックスアンサー No.6509 簡易課税制度の事業区分】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm
- 複数業種の特例(75%特例)
- 2種類以上の事業を営む事業者で、1種類の事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合には、その事業のみなし仕入率を全体の課税売上げに対して適用することができます。
- 3種類以上の事業を営む事業者で、特定の2種類の事業の課税売上高の合計額が全体の課税売上高の75%以上を占める事業者については、その2業種のうちみなし仕入率の高い方の事業に係る課税売上高については、そのみなし仕入率を適用し、それ以外の課税売上高については、その2種類の事業のうち低い方のみなし仕入率をその事業以外の課税売上げに対して適用することができます。
- 例:第2種事業の売上割合60%+第3種事業の売上割合30%+第5種事業の売上割合10%
- 上位2事業(第2種事業と第3種事業)の合計の売上割合=90%≧75% ∴特例適用可
- 原則によるみなし仕入率:
- 第2種事業:80%
- 第3種事業:70%
- 第5種事業:50%
- 特例により適用するみなし仕入率:この場合は原則より特例の方が有利
- 第2種事業:80%
- それ以外の売上:70%
75%特例計算のポイント
- みなし仕入率は、原則により計算するか、75%の特例により計算するかは課税期間ごとに有利な方を選択できます。
- 必ずしも75%特例計算の方が有利になるとは限りません。
2-3. 簡易課税の業種区分の考え方:ミニ判定Q&A
簡易課税の業種区分の考え方をイメージできるように、10種類のミニ判定Q&Aを紹介します。
Q1. 店頭で仕入れた衣料品を一般消費者に販売する場合は?
A1. 第2種事業(小売)。理由:最終消費者への物品販売。
Q2. 仕入れた文具を小売店へ箱単位で販売(B to B)する場合は?
A2. 第1種(卸売)。理由:事業者向けの物品販売。
Q3. 自社で製造したパンを自店舗で販売する場合は?
A3. 第3種(製造等)。理由:自社製造品の譲渡=製造小売。
Q4. 建設工事の請負(内装工事など)を行う場合は?
A4. 第3種(建設・製造等)。理由:工事・製作物の請負。
Q5. レストランで店内飲食を提供する場合は?
A5. 第4種(飲食店業)。理由:飲食の役務提供。
Q6. 仕入れたテイクアウト弁当を一般消費者に販売する場合は?
A6. 第2種(小売)。理由:飲食物でも“物の譲渡”は小売。
Q7. デザイン・翻訳・コンサル報酬を受ける場合は?
A7. 第5種(サービス)。理由:役務の提供。
Q8. 宅配便やタクシーの運賃を受け取る場合は?
A8. 第5種(運輸・通信)。理由:運送に係る役務。
Q9. 事務所用物件を賃貸する場合は?
A9. 第6種(不動産)。理由:事業用不動産の貸付。
Q10. 飲料を自動販売機で販売する場合は?
A10. 第2種(小売)。理由:最終消費者への物品販売。
3. 簡易課税の選択 判断フロー
- 基準期間(基準期間がない法人を含む)の課税売上高が5,000万円以下?
- Yes:2へ
- No:原則課税による計算
- 大型投資の予定がある?
- Yes:納税額シミュレーション・原則課税を検討。(必要に応じて専門家へ)
- No:3へ
- 業種と売上構成からみなし仕入率が実態の課税仕入率を上回る見込み?
- Yes:簡易課税の選択を検討
- No:原則課税の選択を検討
その他の検討ポイント
- 2割特例の対象である事業者、2割特例の対象となる課税期間である場合は、上記も含めて最も有利になる計算方法を検討。
- 簡易課税を適用する場合は、原則2年間は強制適用。単年度だけではなく、複数年度の視点も必要。必要に応じて専門家へ相談。
- 調整対象固定資産や高額特定資産の取得等により、簡易課税制度選択届出書の提出に制限が生じないか確認することも必要。(不明な場合や不安な場合は専門家へ相談。)
4. 簡易課税制度による計算事例
ここでは、簡易課税制度による消費税の納税額の計算がイメージできるよう、2事例を紹介します。なお、ここで紹介する納税額の計算はあくまでイメージしやすいように簡略化しているため、実際の消費税の計算方法とは異なります。
事例A:小売業(第2種・80%)
前提:税抜売上1,000万円(すべて10%対象)
- 売上税額:1,000万円×10%=100万円
- 仕入税額:100万円×みなし仕入率80%=80万円
- 納付税額:100万円−80万円=20万円
- 実際の仕入率が売上に対し80%超であれば原則課税の方が有利。
事例B:飲食店業(第4種・60%)
前提:税抜売上700万円(すべて10%対象)
- 売上税額:700万円×10%=70万円
- 仕入税額:70万円×60%=42万円
- 納付税額:70万円−42万円=28万円
- 実際の仕入率が売上に対し60%超であれば原則課税の方が有利。
5. 簡易課税制度に関するよくある誤り
- 飲食店業を第5種としてしまう(飲食店業は第4種:みなし仕入率60%)。
- 製造小売を単純に小売(第2種)で処理(製造小売は第3種)。
- 設備(固定資産)の売却を卸売(第1種)で処理(固定資産の売却は第4種)。
- 複数事業を運営しているが75%特例を見落としていた(税負担が下がる可能性)。
- 基準期間が5,000万円以下なら自由に簡易課税を選択できると思っていた(簡易課税制度選択届出書の提出が必要)。
6. 簡易課税制度に関するFAQ
Q1. 簡易課税はだれでも選べる?
A1. 基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、「簡易課税制度選択届出書」を提出した場合に適用できます。届出期限は原則「適用したい課税期間の初日の前日まで」。なお、事業を開始した日の属する課税期間については、その課税期間中の提出で当該期間から適用できます。適用をやめる場合は、「簡易課税制度選択不適用届出書」を適用をやめたい課税期間の初日の前日までに提出します。なお調整対象固定資産や高額特定資産の取得等による、簡易課税制度選択届出書の提出の制限に注意してください。
Q2. どんな場合が簡易課税に向いている?
A2. 一般的には、実態の仕入率(=実際の課税仕入の割合)がみなし仕入率以下で、大規模投資や還付見込みがない事業者や、事務負担を軽減したい事業者に向いています。
例えば、小売(第2種80%)・卸(第1種90%)中心で実際の仕入率がこれらのみなし仕入率より低い場合、コンサルなどのサービス中心で課税仕入れが50%未満の場合(第5種50%)などです。
Q3. 2割特例と簡易課税は併用できる?
A3. 同一課税期間に併用計算はできません。例えばその課税期間の消費税の計算について2割特例を選択した場合は、その課税期間については簡易課税の計算はしません。
Q4. みなし仕入率の第◯種事業は、取引ごとに判定するのですか?
A4. 原則は取引単位で判定します。みなし仕入率の区分は、会社全体や部門単位で一律に決めるのではなく、各取引の性質に最も近い第1種事業から第6種事業の区分を当てます。同じ事業者でも、仕入品の小売は第2種、自社製造品の販売は第3種のように、取引の性質で区分は変わります。
Q5. 2業種以上は面倒?
A5. 判定は取引単位が原則で、会社や部門で一律に決めるものではありません。なお、売上構成が単一業種で75%以上(または2業種合算で75%以上)に偏る場合は、「75%特例」によりまとめて計算できます。(上記 2.2 参照)
Q6. 食料品の販売など、軽減税率の売上がある場合は?
A6. 標準税率10%の売上と軽減税率8%の売上に区分して計算します。
Q7. 簡易課税で計算すると還付になることはある?
A7. ありません。簡易課税の仕入税額は売上税額にみなし仕入率を乗じて計算しますから、仕入税額が売上税額を上回ることはありません。ただし、中間納付税額がある場合は、当該中間納付に対して還付税額が発生することはあります。(例:前年度から大幅に売上が減少した場合)
Q8. 簡易課税制度選択届出書を提出すると何年縛られますか?
A8. 原則2年です。
Q9. 簡易課税を選択していますが、基準期間の課税売上高が5,000万円を超えたらどうなりますか?
A9. その課税期間は簡易課税ではなく原則課税で申告することとなります。ただし、簡易課税制度選択届出書の効力自体は残るため、基準期間の課税売上高が5,000万円以下となる課税期間については原則として簡易課税による計算が適用されます。(簡易課税制度選択届出書の効力を失効させるためには、簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要があります。)
7. 改正注意・実務メモ
- 2割特例を適用できる期間は2026年9月30日の属する各課税期間まで。
- 恒久的施設(PE)がない国外事業者は、2024年10月1日以後に開始する課税期間から簡易課税の適用不可。
- 簡易課税制度選択届出の原則:適用したい課税期間の初日の前日まで。開業期はその課税期間中の提出で当該期から適用可。
- 強制適用:簡易課税を選択した場合は原則2年間は継続適用。簡易課税制度をやめる簡易課税制度選択不適用届出は原則やめたい課税期間の初日の前日まで。
- 適用の制限:調整対象固定資産(税抜100万円以上)等の取得や複数年の納税シミュレーションをする必要がある場合は専門家への相談を推奨。
8. おわりに(まとめ)
消費税の簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者にとって、事務負担を大幅に軽減できる可能性がある制度です。
最大の選択基準は、「実態の課税仕入率」と「業種区分ごと(第1種〜第6種)のみなし仕入率」の比較です。みなし仕入率の方が有利(高い)と見込まれる場合、本制度の活用を積極的に検討する価値があります。
ただし、以下の点には十分な注意が必要です。
- 事前届出と2年縛り:適用には原則として事前の届出が必要であり、一度選択すると2年間は強制適用となります。
- 設備投資:多額の設備投資があり、仕入税額が多額になると見込まれる期は、簡易課税では不利になる可能性があるため原則課税の検討も必要です。
- 2割特例との比較:2026年9月30日までの課税期間は、インボイス対応の負担軽減措置である「2割特例」も選択肢となります(該当事業者のみ)。簡易課税と2割特例は併用できず、申告時に有利な方を選択する必要があるため、納税額の比較が重要です。
本記事でご紹介した判断フローや75%特例、業種区分の考え方を参考に、自社の状況(特に投資計画と仕入率)を踏まえて、複数年度の視点で最適な計算方式をご選択ください。
届出のタイミングや固定資産の取得が絡む場合、有利不利の判定に迷う場合は、早めに税理士等の専門家へご相談ください。
9. 参考情報
- 国税庁|No.6505 簡易課税制度(タックスアンサー):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm - 国税庁|No.6509 簡易課税制度の事業区分(タックスアンサー):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm - 国税庁|No.6517 卸売業とされる事業(タックスアンサー):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6517.htm - 国税庁|質疑応答事例 事業の区分方法:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/01.htm - 国税庁|質疑応答事例 簡易課税の事業区分について(フローチャート):
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm - 国税庁|消費税及び地方消費税の申告書・添付書類等:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/shohi/06.htm - 国税庁|インボイス発行事業者の「2割特例」可否フローチャート(PDF):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023010-021.pdf - 国税庁|インボイスQ&A(2割特例関係)(PDF):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
10. 関連内部リンク
💬 Threads(@daichi_tax)で「税と会計の小さな気づき」を短文で発信しています。
👉 https://www.threads.net/@daichi_tax
📘 noteでは読みやすい”3分要約記事”を更新中です。
👉 https://note.com/daichitax