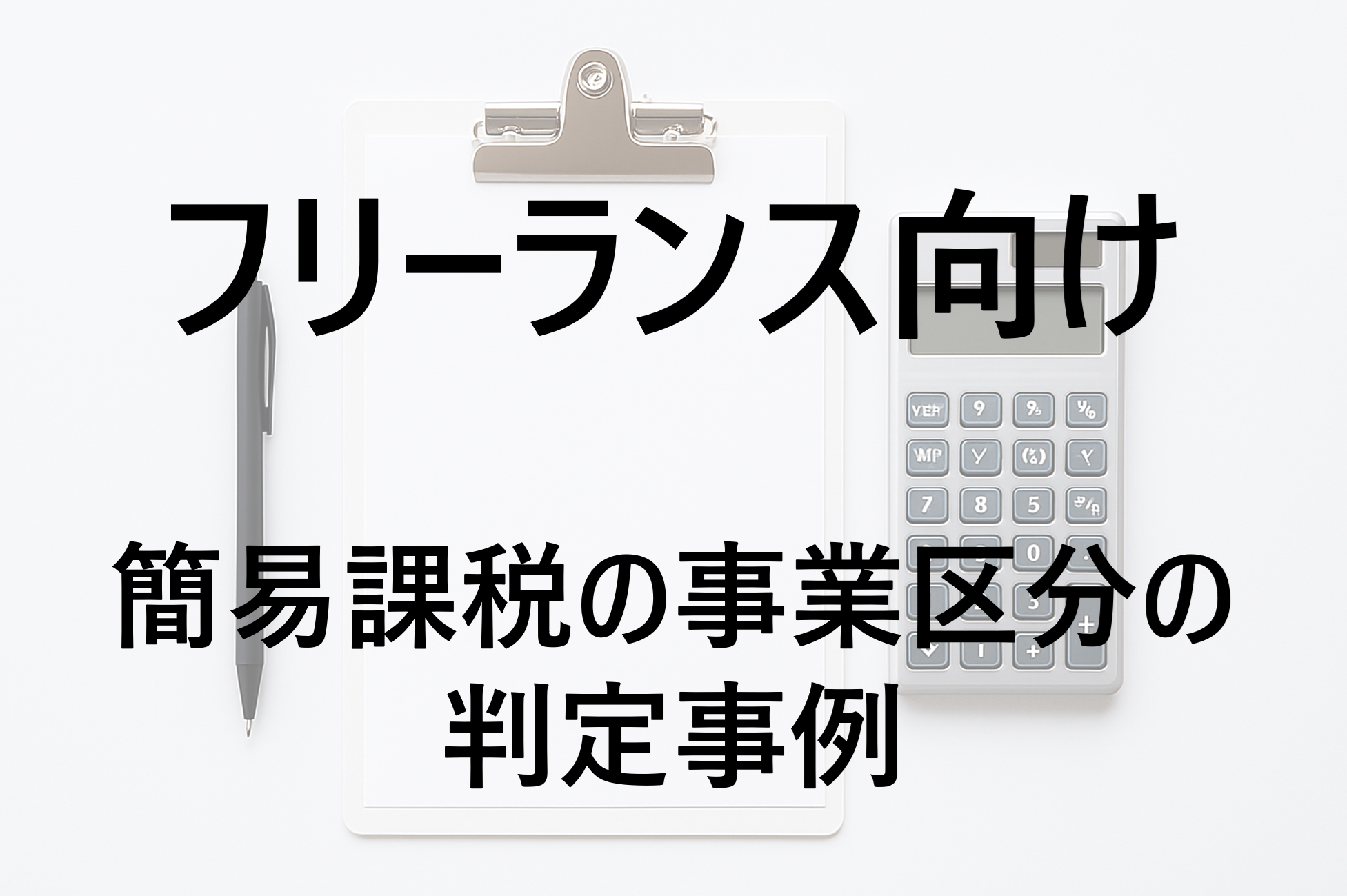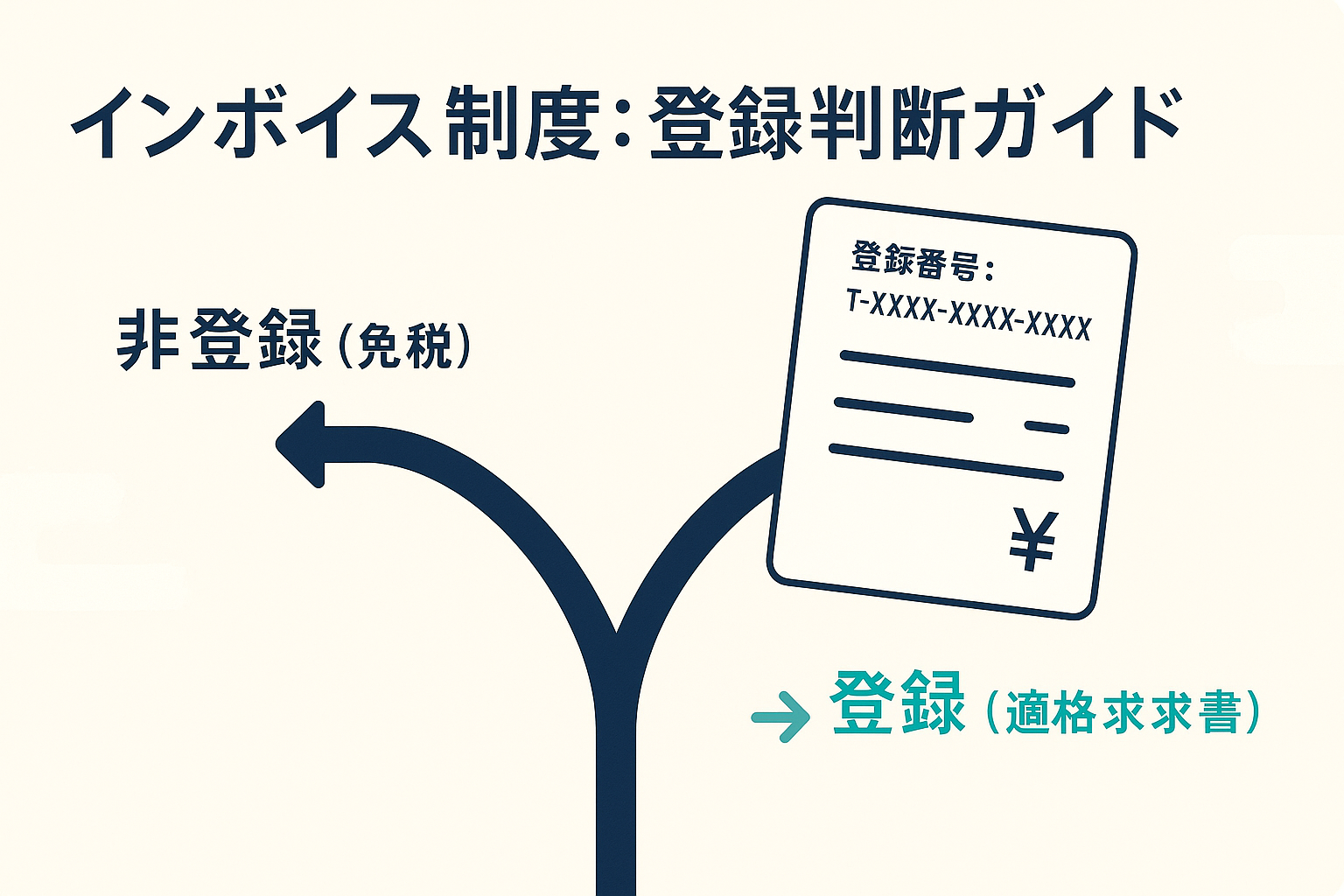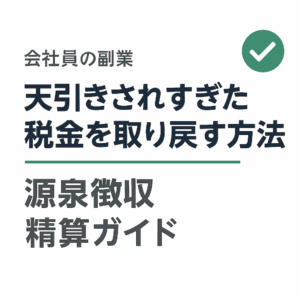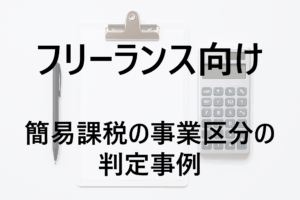簡易課税の事業区分の考え方ガイド
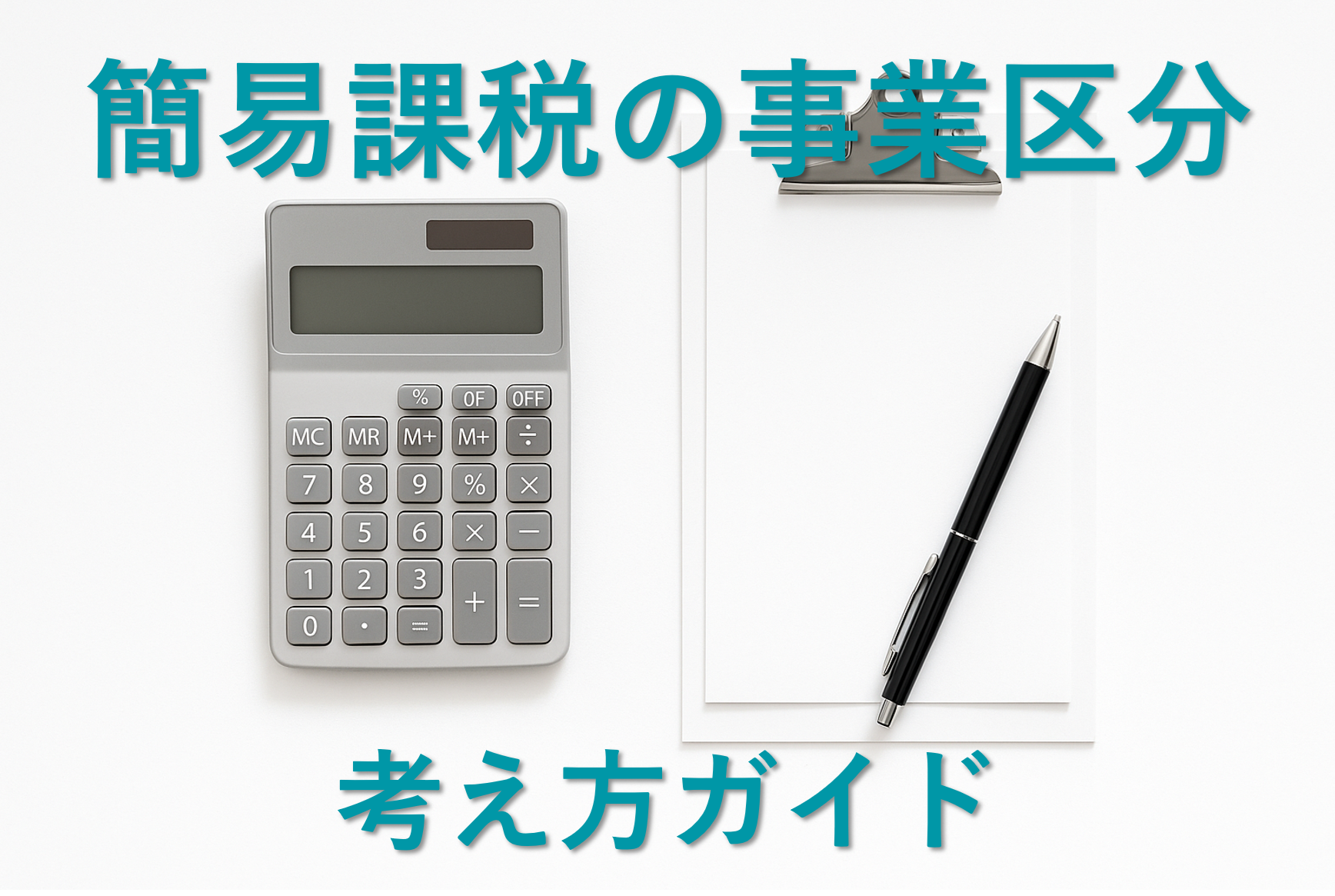
消費税・簡易課税の「事業区分」で迷う方へ。第1種事業~第6種事業の定義、判定手順、代表例、迷いやすい境界を体系的に整理。実務で使える「考え方」に特化して分かりやすく解説します。
本記事は、一般的な概要と選択肢について解説するものです。特定の個人・法人に対する税務アドバイスを提供するものではありません。制度の適用や具体的な税務判断にあたっては、必ず最新の法令等をご確認いただくか、税理士等の専門家または所轄税務署にご相談ください。
Contents
簡易課税の事業区分の考え方(結論)
- 簡易課税の事業区分は、税額の結果を左右する重要な基礎になります 。
- 事業区分の判定は必ず「取引単位」で行い、卸/小売、製造小売、飲食、不動産等の代表的な境界を理解することが大切です 。
- 最終判断は取引の実態に基づき、迷った際は国税庁の情報で裏付け、判断根拠を記録しましょう 。
この記事の想定読者/到達目標
想定読者:
簡易課税を選択中/検討中の中小事業者・個人事業主、経理担当者、税務初心者の方。
到達目標:
自社の各取引をどの事業区分で扱うかを理解でき、迷う場面で参照すべき一次情報へすぐ当たれる。
1. 簡易課税の事業区分
簡易課税の「事業区分」は、課税の対象となる売上等の内容を第1種事業~第6種事業へ分類する考え方です。判定は原則として取引ごと(取引単位)に行います。会社や店舗単位ではなく、売上の内容ごとに区分する点がポイントです。
【国税庁 簡易課税制度の事業区分の表】
事業区分 | みなし仕入率 | 該当する事業 |
|---|---|---|
第1種事業 | 90% | 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 |
第2種事業 | 80% | 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第1種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。 |
第3種事業 | 70% | 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第1種事業、第2種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。 |
第4種事業 | 60% | 第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。 |
第5種事業 | 50% | 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第1種事業から第3種事業までの事業に該当する事業を除きます。 |
第6種事業 | 40% | 不動産業 |
2. 簡易課税の事業の区分の方法
複数の事業がある場合は、例えば次のような方法で区分します。客観的に確認できる状況で区分されていれば、その方法で構いません。
なお、2種類以上の事業を行い、一方の事業が明確に区分されているときは、残りの区分されていない課税売上高はもう一方の事業として区分して構いません。(3種類以上の場合も同様)
- 帳簿等に事業の種類を記載して区分する方法
- 納品書・請求書・売上伝票の控え等に事業の種類(記号等でも可)を記載し、かつ区分ごとの課税売上高を集計した記録を保存する方法
- レジペーパー(POS)に品番等が印字されるものについて、その印字により区分し、かつ区分ごとの課税売上高の集計記録を保存する方法
- 事業場ごとに一種類の事業のみを行っている場合には、事業場ごとの課税売上高を集計する方法
3. 簡易課税の事業区分の判定の基本原則
- 取引単位判定:売上等の性質(誰に/何を/どう提供したか)で判断。登記業種や社名では決めない。
- 無加工販売:相手が事業者なら卸売(第1種事業)、最終消費者等なら小売(第2種事業)。
- 軽微な加工の小売:食料品小売で店舗内の一般的な軽微加工(カット・盛付・量り売り等)をして同一店舗で販売する場合は第2種事業の範囲。
- 製造等:自社で製造・加工して販売(製造小売)する場合は第3種事業。建設や製造問屋も原則第3種事業に含まれる。
- 役務提供のうち「飲食の提供」:レストラン等の飲食提供は第4種事業。ホテルの宴会・ケータリングも飲食提供として扱う。
- 不動産関連:賃貸・仲介・管理=第6種事業/販売=実態で第1・第2・第3種事業(仕入再販=第1・第2種事業/自社施工・中古リメイク=第3種事業)
- 固定資産の売却:第4種事業。
- 不明な場合:国税庁が公表している質疑応答事例等で確認する。
4. 簡易課税の事業区分の判定事例(境界の考え方)
- ケーキ店+喫茶スペース(製造小売+喫茶)
→ 自社製造品の店頭販売は第3種事業、店内での飲食提供は第4種事業。同一会計内でも取引単位で区分し、レジ区分や会計伝票で根拠を残す。 - クリーニング業
→ 顧客の物品に対する加工賃等を対価とする役務提供のため第5種事業。物販を併営する場合は別取引(第1種事業又は第2種事業)として区分。 - 固定資産の売却(機械・車両・器具備品等)
→ 本業の如何を問わず自社固定資産の譲渡は第4種事業。課税・非課税(土地の売却など)の判定にも注意。 - 業務用販売(卸と小売の峻別)
→ 無加工販売で、相手が事業者と帳簿等で明らかなものは第1種事業、それ以外は第2種事業。会員登録や請求書先の管理で取引先の属性を明確に。 - 飲食店・ケータリング
→ 店内飲食や宴会、ケータリング等の飲食の提供は第4種事業。宿泊や会場使用料等とのセット料金は対価の区分に注意。 - 不動産取引(賃貸・仲介・販売・リフォーム)
→ 賃貸・仲介・管理は第6種事業、販売は実態で判定(仕入れてそのまま販売=第1種事業又は第2種事業、自社施工や中古住宅のリメイク販売=第3種事業)。リフォーム等の工事請負は第3種事業、自社で使っていた不動産の売却=第4種事業。 - 情報通信業(受託ソフト開発・情報処理)
→ プログラムの作成・保守、運用支援等は役務提供に該当し第5種事業。 - セミナー+教材(複合取引)
→ 対価を区分している場合は、参加費=第5種事業(サービス)/教材代=物の販売として判定(事業者向け=第1種事業、消費者向け=第2種事業、自社で製作・出版した教材の販売=第3種事業の可能性)。対価を区分していない場合は、全額を第5種事業(教材は付随)として扱うのが原則。 - 旅館・ホテル(宿泊+飲食)
→ 対価の区分がない宿泊+食事プランは全額第5種事業(宿泊)。区分されていれば、食事部分のみ第4種事業。 - 駐車場業(時間貸し・月極)
→ 土地の貸付のうち駐車場としての貸付は課税対象で第6種事業。管理委託や機械設備の利用を含む契約は実態(不動産の貸付か、役務か)で確認。
▶フリーランス向け|簡易課税の事業区分の判定事例を以下の記事で紹介しています。
5. 簡易課税の事業区分に関するよくある誤り
- 会社の主業で判定してしまう → 正しくは取引単位で判定。
- 業務用に売った小売を一律で第2種事業にする → 相手が事業者と明らかなら第1種事業(卸売)。
- 軽微な加工=製造と誤解 → 食料品の一般的な軽微加工は第2種事業の範囲。
- 製造小売を第2種事業にしてしまう → 正しくは第3種事業。
- 固定資産売却を本業区分に入れる → 正しくは第4種事業。
- 課税対象となる雑収入や固定資産売却収入を除いて計算してしまう → これらも含めて計算。
6. 簡易課税の事業区分に関するFAQ
Q1. 区分判定は会社全体で一つにまとめますか?
A1. いいえ。売上等(取引)ごとに判定します。
Q2. ネット販売で企業にも個人にも売る場合は?
A2. 無加工販売であれば、企業向けは第1種事業、個人向けは第2種事業に取引単位で区分します。
Q3. 製造して自店で販売する(製造小売)は?
A3. 第3種事業です。
Q4. 飲食店のテーブル提供は?
A4. 第4種事業です(宴会・ケータリングも同様に飲食提供として扱います)。
Q5. 業務用スーパーは第2種事業ですか?
A5. 相手が事業者と明らかなら第1種事業(卸売)に該当し得ます。証憑管理が鍵です。
Q6. 軽微な加工(量り売り・簡易調理)をした食材販売は?
A6. 同一店舗での一般的軽微加工なら第2種事業で差し支えありません。
Q7. 不動産賃貸業は?
A7. 第6種事業です。
Q8. 自社の不要設備・車両を売った場合は?
A8. 第4種事業です(自社固定資産の譲渡)。
Q9. 複数区分がある場合、全部細かく分けないとダメ?
A9. 原則は区分ごと集計。ただし売上の75%以上が1区分であれば、その区分のみなし仕入率を全体に適用できる特例があります。さらに3区分以上で、上位2区分の合計が75%以上の特例もあります。
Q10. 迷ったらどの資料を見るべき?
A10. 簡易課税の事業区分については、国税庁のHPで事業区分の考え方や、フローチャート、日本標準産業分類からみた事業区分などの考え方が紹介されています。これらの国税庁HPへのリンク先はこの記事の「9. 参考情報」に載せておりますので参考にしてください。
7. 改正注意・実務メモ
- 日本標準産業分類:総務省の日本標準産業分類の改定に合わせ、国税庁の「日本標準産業分類からみた事業区分」も更新されます。該当大分類ページの現在法令等年月を併せて確認すると安全です。
- 75%特例:複数事業区分があるのときのみなし仕入率一括適用(75%)特例の有無で税額計算の結果が変わることがあります。試算段階で両案を比較検討しましょう。
8. おわりに(まとめ)
簡易課税の事業区分は、簡易課税による消費税の納税額に直結する重要な基礎になります 。判定は会社全体ではなく「取引単位」で売上等の性質を見極めること 、そしてその事業区分を国税庁のHP等でよく確認することです。
特に、卸売と小売の区分 、製造小売(第3種事業)、飲食提供(第4種事業)、固定資産売却(第4種事業)は、実務で迷いやすい代表的な例です 。
最終的な判断は、取引の実態に基づきます 。判断に迷う点は必ず国税庁の最新情報で裏付けを取るか、不安な場合は専門家へ相談し、判断根拠を記録しながら運用しましょう 。
9. 参考情報
- 国税庁 タックスアンサー No.6509 簡易課税制度の事業区分:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm - 国税庁 質疑応答事例 事業の区分の方法:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/01.htm - 国税庁 質疑応答事例 簡易課税の事業区分について(フローチャート):
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/02.htm - 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度(75%特例を含む):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm - 国税庁 質疑応答事例 日本標準産業分類からみた事業区分:
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/03.htm(農業・林業他)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/04.htm(製造業)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/05.htm(電気業・情報通信業他)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/06.htm(卸売業・小売業)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/07.htm(金融業・保険業・不動産業・飲食サービス他)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/08.htm(生活関連サービス業他)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/09.htm(教育・複合サービス・サービス業他) - 国税庁 パンフ 事業区分の判定フローチャート(PDF):
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/pdf/02-10.pdf - 国税庁 消費税法基本通達(第13章:簡易課税/第2節 事業区分の判定):
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/13/02.htm - 総務省 日本標準産業分類:
https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
関連内部リンク
💬 Threads(@daichi_tax)で「税と会計の小さな気づき」を短文で発信しています。
👉 https://www.threads.net/@daichi_tax
📘 noteでは読みやすい”3分要約記事”を更新中です。
👉 https://note.com/daichitax