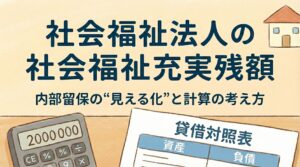土地改良区の理事・監事が押さえるべき法的責任とリスク管理|「ボランティア役員」では済まされない立場とは?

土地改良区の役員は、地域の信頼を背負った大切な役割です。
一方で、「頼まれて引き受けただけ」「よく分からないまま理事・監事になってしまった」という声も少なくありません。
この記事では、土地改良区の理事・監事が最低限おさえておきたい 法的責任とリスク管理のポイント を、専門用語はできるだけ避けながら整理します。新任役員の方にも、改めて整理したいベテランの方にも読んでいただける内容を意識しました。
Contents
この記事の想定読者
- 土地改良区の理事・監事に就任したばかりの方
- 土地改良区の事務局長・事務担当者など、役員を支える立場の方
- これから土地改良区の役員に就任するよう依頼されている組合員の方
1. 土地改良区の役員は「ボランティア」ではない
土地改良区は、土地改良法に基づき都道府県知事の認可を受けて設立される 公法人です。
土地改良法13条で「土地改良区は、法人とする」とされ、10条・12条で都道府県知事の認可による設立手続が定められています。
社団法人(組合)の性格を持ちながら、
- 組合員の強制加入制度があること(第3条の資格者は第11条により自動的に組合員となる)
- 事業が地域の水管理や農業生産に直結すること
などから、しばしば「地方公共団体に準じる性格を持つ公共的団体」と説明されます。
一方で、農業者の自主的な協同組織という側面も併せ持っています。
その運営を担うのが、理事・監事をはじめとする役員です。
「地域のための持ち回り」「頼まれたから断りづらくて…」というお気持ちはあっても、法的には次のような重い責任を負っています。
- 土地改良区の業務を適正に運営する義務
- 法令・定款・規約・総代会(総会)の決議を守る義務
- 義務違反があった場合の損害賠償責任 等
つまり、善意のボランティアだから責任が軽いとは扱われません。ここをまず共有したうえで、具体的な役割と責任を見ていきます。
2. 理事・監事の基本的な役割と権限
2-1. 理事の役割
土地改良法18条・19条では、土地改良区には役員として 理事と監事を置くこと、そして理事が土地改良区を代表して事務を執行することが定められています。
理事の主な役割は、次のとおりです。
- 土地改良区の 業務執行の中心 を担う
- 区を代表して契約を結ぶなどの 代表権 を持つ
- 総代会・理事会で決定された方針を、日々の業務に具体化する
また、土地改良法18条2項では、
- 理事は原則 5 人以上
- 監事は原則 2 人以上
置くこととされ、同条5項では、
- 理事定数の少なくとも 5 分の 3 は、当該土地改良区の組合員であり、かつ耕作または養畜の業務を営む者
であることが求められています。組合員の代表としての性格が強いポジションといえます。
2-2. 監事の役割
監事は、ひと言でいえば 「理事の仕事ぶりと土地改良区の財産をチェックする役」 です。
主な役割は次のとおりです。
- 理事の業務執行状況の監査
- 土地改良区の財産状況の監査
- 必要な場合、是正を求めたり総代会等に報告したりすること
さらに土地改良法21条では、土地改良区と理事との間の契約・争訟については、監事が土地改良区を代表する と定められています。これは、理事自身に関わる問題を、理事が自分の都合で処理してしまうことを防ぐための仕組みです。
また、土地改良法18条6項では、監事のうち 1 名以上を「員外監事」(組合員やその親族・関係法人等ではない者)とすることが原則とされています。
ただし、公認会計士や税理士、都道府県土地改良事業団体連合会などから継続的な専門指導を受けている場合などには、員外監事を置かないことができるとする例外規定もあります。
3. 役員が負う 3 つの基本義務
土地改良区の役員の義務は、土地改良法と民法の両方から説明されますが、実務感覚としては次の 3 つに整理すると分かりやすくなります。
とくに土地改良法19条の5では、役員の基本的な義務と責任がまとめて規定されています。
(1) 善管注意義務(善良な管理者の注意義務)
土地改良法19条の5第1項では、役員は「法令、行政庁の処分、定款、規約、管理規程、利水調整規程及び総会決議を遵守し、土地改良区のため忠実に職務を遂行しなければならない」とされています。
一方、民法644条では、委任を受けた者に対して「善良な管理者としての注意」=善管注意義務が課されています。
条文上、土地改良法自体に「善管注意義務」という用語は出てきませんが、これらの規定や役員の立場を踏まえ、実務上は 少なくとも善管注意義務と同等以上の注意義務が求められる と理解されています。
土地改良区の役員も、区から業務を託された立場であり、普通の組合員よりも一段高い注意レベルが求められます。具体的には、
- 重要な数字・資料はきちんと確認する
- 分からない点はその場で質問する
- 気になる点を「まあいいか」と流さない
といった姿勢です。「忙しかったから」「よく分からなかったから」という理由では、責任を免れにくいのが実務上の感覚です。
(2) 忠実義務(土地改良区のために働く義務)
役員は、土地改良区の利益のために忠実に職務を行う義務 を負います。これは前述の土地改良法19条の5第1項にも明記されています。
具体的には、
- 自分や特定の組合員だけが得をするような意思決定をしない
- 個人的な利害よりも、区全体の利益を優先する
- 総代会の決議や事業計画に沿って運営する
といった姿勢が求められます。
「自分の圃場だけ優先して整備する」「親しい業者だけを優先する」といった行為は、忠実義務違反と評価されるおそれがあります。
(3) 法令・定款・規約・総代会決議の遵守義務
土地改良法19条の5第1項は、役員が遵守すべきルールとして、
- 法令
- 行政庁の処分
- 定款
- 規約
- 管理規程
- 利水調整規程
- 総会決議
を列挙しています。これに加えて、行政の通知やガイドラインなど、いわば「守るべきルール」は多数あります。
役員には、
- これらのルールを理解し、
- ルールに沿って業務を進めるよう、事務局を監督する
という役割があります。
「よく知らなかった」「昔からこうやっているから」で済ませてしまうと、任務懈怠(義務を怠った) と評価されるリスクがあります。
4. 責任追及が問題になる典型パターン
では、実際に役員の責任が問題になるのはどのような場合でしょうか。ここでは、よくあるパターンをイメージしやすい形で整理します。
4-1. 土地改良区に対する責任(内部責任)
土地改良法19条の5第2項では、役員がその任務を怠ったときは、役員は土地改良区に対し、これによって生じた損害を連帯して賠償する責任を負うと定められています。
典型的には、次のようなケースが考えられます。
- 明らかに不利な条件で長期契約を締結し、多額の損失を出した
- 賦課金の徴収や滞納管理を事実上放置し、大きな未収金を発生させた
- 会計処理のルールを守らず、不適切な支出・貸付を容認した
「理事会で決めたから自分の責任ではない」という主張は通らず、理事会の一員としての注意義務 が問われます。
4-2. 第三者に対する責任(外部責任)
土地改良法19条の5第3項では、役員がその職務に関し 悪意または重大な過失 により第三者に損害を与えたときは、第三者に対しても連帯して損害賠償責任を負うとされています。
イメージしやすい例としては、
- 施設の老朽化を把握しながら安全対策を怠り、決壊や事故を招いた
- 排水路の管理を怠り、下流の農地や民家に被害を与えた
- 明らかに違法な支出・処理を黙認し、関係者や行政に損害を与えた
などがあり得ます。
4-3. 監事が責任を問われやすいパターン
監事は「チェック役」でありながら、その役割を十分に果たしていないときにも責任が問われます。
例えば、
- 決算書や帳簿に明らかな不自然さがあるのに、深く調べない
- 重大な疑義を感じても、理事会や総代会に報告しない
- 監査結果の指摘事項を、その後フォローしない
など、「見て見ぬふり」「形だけの監査」と評価されると、監事自身も任務懈怠を指摘されるおそれがあります。
5. 今日から始めるリスク管理(理事会・監事・事務局それぞれのポイント)
責任が重いことは分かっても、「では具体的に何をすればいいのか」が分からないという声も多く聞かれます。
ここでは、今日から実践できるリスク管理の視点 を、役割別に整理します。
5-1. 理事会としての取り組み
- ルールの棚卸し
定款・規約・会計細則・管理規程・各種内規を整理し、最新版を役員全員が共有する。 - 重要案件は必ず議事録を残す
多額の契約、賦課金の見直し、施設更新などは、「誰が」「どの情報をもとに」「どう判断したか」を議事録で残す。 - 事務局任せにしない
予算・決算・資金繰り、主要な契約については、必ず理事会で説明を受ける。
「前からこうだから」で済ませず、疑問点はその場で確認する。
5-2. 監事としての取り組み
- 監査計画を作る
年に何回、どの範囲を監査するか、簡単でも良いので計画に落とし込む。 - リスクの高い分野に重点を置く
資金・預金・借入、賦課金の算定と徴収、施設の維持管理・更新など、「金額が大きい」「外部への影響が大きい」分野に時間を割く。 - 指摘事項のフォローアップ
監査で指摘した事項について、「その後どう改善されたか」を次回監査で必ず確認する。
5-3. 事務局としての取り組み
- 手続・フローの「見える化」
予算から決算までの流れ、契約締結の決裁ルート、賦課金の徴収フローなどを図解・文書化する。 - ダブルチェックの仕組み
現金・預金の出納、契約書の締結などは、必ず複数の目で確認する仕組みを作る。 - 役員研修への協力
新任役員向けの説明資料を準備し、役割・責任・最近の注意点を整理して説明する。
6. 最近の法改正の動きにも注意を
土地改良法等については、平成30年法律第29号による改正(いわゆる平成30年改正)や、令和7年法律第14号による改正(令和7年4月1日施行)などにより、定款例や関連通知の見直しが進められてきました。
- 定款例・規約例の改正
- 運営・検査・会計に関する通知の見直し
など、今後も、法令そのものだけでなく、運用に関するガイドラインも変わる可能性があります。
理事・監事としては、
- 都道府県や土地改良事業団体連合会が実施する研修・説明会
- 農林水産省や都道府県の通知・解説資料
に注意を払い、最新のルールにアップデートされた定款・規約になっているか を確認することが大切です。
7. まとめとセルフチェックリスト
7-1. まとめ
- 土地改良区は公法人として強い公共性を持つ団体であり、役員には相応の法的責任が課されている。
- 理事は業務執行と代表、監事は監査と是正・報告という役割分担がある。
- 土地改良法19条の5に基づき、善管注意義務と同等以上の注意義務・忠実義務・ルール遵守義務を怠ると、土地改良区に対する損害賠償責任や、第三者に対する損害賠償責任を負う可能性がある。
- 日頃から、議事録・監査・内部牽制・ルール整備といった地道なリスク管理が、役員を守り、土地改良区を守ることにつながる。
- 法改正・通知改正の動きにも目を配り、定款・規約を「今の時代に合ったもの」に保つことが重要である。
7-2. セルフチェックリスト(Yes / No)
- 自分の土地改良区の定款・規約・会計細則を、最近 1 年以内にきちんと読んだことがある。
- 理事会・総代会の議事録は、決定の経緯や反対意見も含めて、きちんと残されている。
- 大口の契約や施設更新について、複数の見積や比較検討のプロセスが確立している。
- 監事として、年度初めに監査計画を作る運用になっている。
- 監査での指摘事項について、改善状況のフォローアップを行っている。
- 賦課金の算定・徴収・滞納管理について、現状のリスクを説明できる。
- ここ数年の法改正・通知改正のポイントを、役員同士で共有している。
「No」が多い項目ほど、リスクが潜んでいる可能性が高い部分です。一度、理事会・監事・事務局で話し合ってみる価値があります。
8. 参考情報
- e-Gov 法令検索「土地改良法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000195 - 農林水産省「土地改良区定款例」「土地改良区規約例」
https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000381.html
https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000382.html
9. 関連内部リンク
💬 Threads(@daichi_tax)で「税と会計の小さな気づき」を短文で発信しています。
👉 https://www.threads.net/@daichi_tax
📘 noteでは読みやすい”3分要約記事”を更新中です。
👉 https://note.com/daichitax