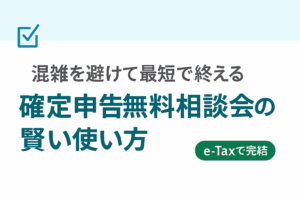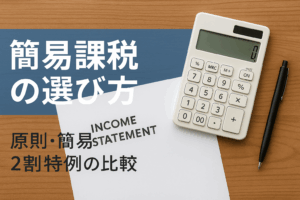フリーランスのための社会保険の知識(国民健康保険編)
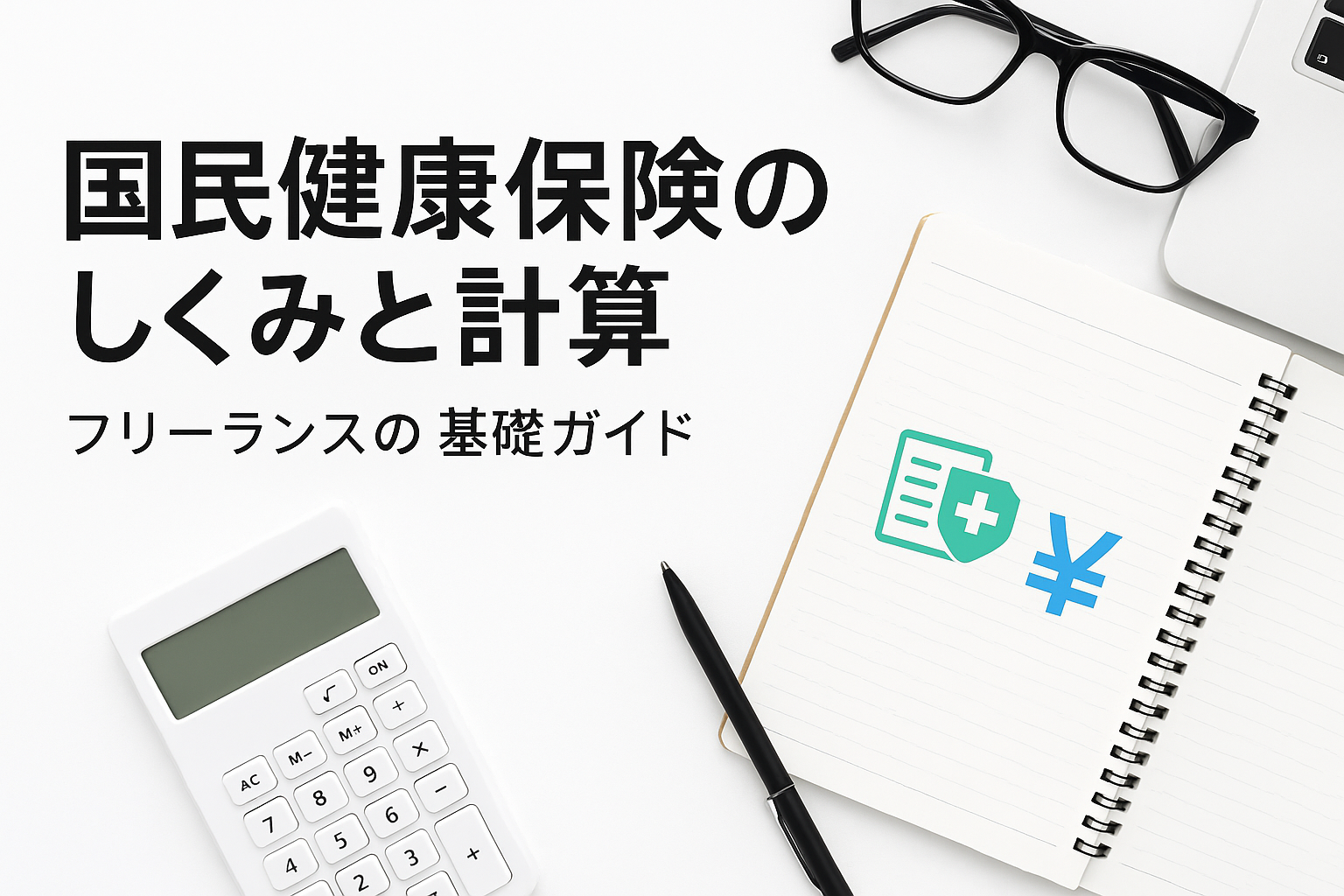
フリーランスになった瞬間、会社の社会保険という“傘”は外れます。では何に入り、いくら払うのか。この記事は国民健康保険を中心に、会社員との違い、算定方法のイメージ、簡易試算の手順、コストを下げる打ち手までを一気に整理。今日から迷わないための入口ガイドです。
Contents
1. 結論
1-1. 3つのポイント
- 前提:フリーランスは基本が国民健康保険(国保)+国民年金。国保は世帯単位・扶養なし・自治体差が大きいため、最初に「自分はどの制度に入るか」「家族はどこに入るか」を整理する。
- 計算のキモ:国保料は前年の総所得金額等−基礎控除(多くは43万円)をベースに、所得割+均等割+平等割(自治体差)で決まる。iDeCo・小規模企業共済・税額控除などは国保の賦課に直接効かない。国保の削減に効くのは所得金額そのものを下げる施策(経費整備・青色65万円等)と各種軽減の活用。
- 実務の打ち手:正しい記帳と青色申告特別控除の最大化、未就学児半減・失業軽減・低所得軽減などの申請が中心。必要に応じて国保組合・会社健保の扶養も検討。正確な額は必ず自治体の試算で確認。
1-2. 税金 vs 国民健康保険(国保):どれが効く?
- 税金・国保の両方に効くもの
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 必要経費の適正計上・家事按分の見直し:あくまで適正な見直しが前提
- 税金(所得税・住民税)のみに効くもの(国保には効かない)
- iDeCo/小規模企業共済(所得控除)
- 生命保険料控除(所得控除)
- 社会保険料控除(所得控除)
- 扶養控除など(所得控除)
- ふるさと納税(税額控除)
2. この記事でわかること
- 国保と会社健保の決定的な違い
- 賦課基準額(総所得金額等−基礎控除)の見方
- 保険料のざっくりとした計算方法
- 国保を下げる打ち手
3. フリーランスの社会保険、全体像(ざっくり)
3-1. フリーランスの社会保険の全体像
フリーランス(個人事業主)は、会社員の「社会保険(健康保険・厚生年金)」とは加入制度が異なります。
- 医療
- 病気やケガの治療費を“みんなで割る”仕組み。保険証で窓口負担が軽くなる(年齢などで割合は変動)。
- 多くは国民健康保険(国保)に加入(市区町村が窓口、都道府県単位で財政運営)。国保以外に、業界によっては国民健康保険組合(文芸美術国保、建設国保など)に加入できる場合もあります(保険料・給付が別枠)。
- 年金
- 老後・障害・遺族の生活を支える長期の所得保障。フリーランスは国民年金が基本、必要に応じて付加年金やiDeCoで上積み。
- 原則国民年金(1号被保険者)。付加年金やiDeCoの活用で老後給付の底上げを検討。
- 労災・雇用
- 仕事中・通勤中の災害や失業期間を支える制度。フリーランスは労災に特別加入可。雇用保険は原則対象外だが、離職した元会社員には国保の失業軽減が使える場合あり。
- 労災の特別加入:現場・運搬など事故リスクが高い一人親方等、業務委託型の特定受託事業者、従業員を雇って労災を適用する中小事業主等が中心。デスクワーク中心のソロは優先度低め。必要に応じて特別加入団体経由で検討。
ポイント
制度の“入口”が会社経由か自分で手続きか、が最初の分かれ目。フリーランスは原則「自分で加入・申請」する。
用語メモ
自治体によっては「国民健康保険料」を「国民健康保険税(国保税)」と表記します。本記事では読みやすさのため国民健康保険料(国保)に統一しています。呼称は異なっても、計算の基本構造(所得割・均等割・平等割・介護分)や軽減の考え方は同じです。詳細はお住まいの自治体の案内をご確認ください。
※法令上の根拠(「料」=国民健康保険法/「税」=地方税法)に基づく呼称の違いはありますが、本記事の範囲(試算・比較・制度理解)では実務上の差はありません。
3-2. 判断フロー(自分/家族はどこに入る?)
- 直近2年以内に会社員だった → 任意継続の条件・保険料を確認。
- 配偶者が会社員か → 条件を満たせば会社健保の扶養に、満たさなければ国保へ。
- 自分が加入できる国保組合があるかを確認(業界団体)(国保より国保組合の方が保険料が高ければ加入不要)。
- 上記に当てはまらなければ市区町村の国保(本記事の対象)。
補足:後期高齢者医療・介護保険について
本記事は現役フリーランス向けに国保中心に解説します。75歳以上は後期高齢者医療制度(別制度)に加入します。介護保険は40〜64歳は国保料に介護分が上乗せ、65歳以上は年金からの特別徴収(天引き)が原則です。
4. 国民健康保険の仕組み(サラリーマンとの違い)
| 項目 | 国民健康保険 (国保) | 会社の健康保険 (協会けんぽ・健保組合 等) |
|---|---|---|
| 窓口・運営 | 市区町村が窓口/ 都道府県単位で財政運営 | 事業所経由で加入/ 協会けんぽ・健保組合・共済 等 |
| 加入対象 | 会社の健保に入らない人 (フリーランス・無職 等) | 会社員・公務員 等 |
| 扶養の扱い | 扶養なし (加入者が増えると保険料も増える) | 被扶養者の保険料負担なしが基本 |
| 保険料の算定 | 前年の賦課基準額×保険料率 +均等割・平等割等 (自治体差) | 標準報酬月額ベース (賞与も反映) |
| 負担の仕方 | 全額自己負担 (世帯として) | 会社と折半 |
| 計算単位 | 世帯単位 (世帯で合算) | 個人単位 (被保険者ごと) |
| 軽減・独自制度 | 低所得軽減/未就学児の均等割半減/失業軽減 など (要申請・自治体差) | 組合独自の付加給付や保健事業あり (組合差) |
| 40〜64歳の介護分 / 75歳以降 | 40〜64歳は介護分上乗せ/75歳〜は後期高齢者医療へ | 同様に介護保険料あり/退職後は任意継続など |
料率
自治体・健保組合ごとに細部(料率・上限・付加給付)が異なります。正確な額は各サイトで要確認。
ワンポイント
国保の保険料は「医療分・後期高齢者支援金分・(40〜64歳は)介護分」の合計で、各分は「所得割・均等割・平等割(※平等割なし/資産割ありの自治体も)」の組合せ。
5. 国民健康保険(国保)の計算(ざっくり)
5-1. 保険料の算定基礎(賦課基準額)を算出
- 賦課基準額は前年の総所得金額から基礎控除を差し引いた額がベース。
- 基礎控除は多くの自治体で43万円(高所得者は段階的に減額)。
ポイント(「前年の総所得金額」の確認)
- 対象年・対象者:当年度の国保料は前年分の所得で算定。世帯の国保加入者全員を合算(軽減判定で世帯主を見る自治体あり)。
- 確認箇所:確定申告書の「所得金額 合計」/申告なしは住民税の課税決定通知書の「総所得金額等」。
- 対象所得:事業・給与・不動産・雑・総合の配当・分離の譲渡等を含む/一時所得は特別控除後の1/2/退職所得は通常対象外。
- 賦課のベース:賦課基準額=総所得金額等 − 基礎控除(多くは43万円)。iDeCo等の所得控除・税額控除は賦課に直接効かない一方、経費・青色申告特別控除は効く。
5-2. 保険料の計算の全体像
- 国民健康保険の各区分ごとに保険料を計算します。
- 区分には、所得割、均等割、平等割などの区分があります。
- 各区分には上限があり、上限を超えた場合はその上限までの額になります。
| 区分 | 所得割 | 均等割 | 平等割 (無い自治体あり) | 合計 |
| 医療分 | 賦課基準額× 医療分の料率 | 加入者数× 医療分の均等割単価 | 世帯あたり定額 | 医療分の合計 (上限を超える場合は上限まで) |
| 後期高齢者 支援金分 | 賦課基準額× 支援金分の料率 | 加入者数× 支援金分の均等割単価 | 世帯あたり定額 | 支援金分の合計 (上限を超える場合は上限まで) |
| 介護分 (40〜64歳) | 賦課基準額× 介護分の料率 | 介護対象人数× 介護分の均等割単価 | 世帯あたり定額 | 介護分の合計 (上限を超える場合は上限まで) |
| 国民健康保険料の合計 | ー | ー | ー | 上記の合計 =国民健康保険料 |
自治体によって異なります
- 一部自治体では資産割(固定資産税割)を採用している場合があります。また、自治体によって区分や料率は異なるため、具体的な国民健康保険料の計算方法はお住まいの自治体ページで確認してください。
- 毎年6月頃にお住まいの自治体から国民健康保険料(税)納入通知書が届きます。ご自身の国民健康保険料がどのように計算されているのか確認してみましょう。
5-3. 保険料の軽減・減免
- 低所得軽減(7割・5割・2割):世帯所得が基準以下なら、均等割・平等割を段階軽減。
- 未就学児の均等割半減(2024年度以降全国的に導入)。
- 失業軽減:倒産・解雇等の離職(特定受給資格者・特定理由離職者)なら、前年給与所得を30%とみなす扱い。要申請。
ポイント
自治体ごとに保険料率・区分の上限・軽減の設計が異なるため、正確な金額は必ず居住自治体のページで試算・確認してください。
5-4. (参考)保険料比較(船橋市/函館市/青森市/横浜市)
参考までに、令和7年度の国民健康保険料について、船橋市、函館市、青森市、横浜市で比較してみました。
<比較の前提条件(すべて架空の数値)>
- 家族構成:世帯主(事業所得者)/配偶者(所得なし)/子(12歳)/子(10歳)
- 事業所得(青色申告特別控除後):5,000,000円
- 加入者数:4名(うち40歳以上2名=世帯主と配偶者は介護分の保険料の支払対象)
- 基礎控除:430,000円
- 賦課基準額:4,570,000円(=5,000,000 − 430,000)
- 加入期間:12か月
<国民健康保険料の算出表(令和7年度・比較:船橋市/函館市/青森市/横浜市)ざっくり>
| 項目 | 計算方法 | 船橋市 | 函館市 | 青森市 | 横浜市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所得金額① | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 基礎控除② | - | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 |
| 子ども控除(横浜市独自:19歳未満1人33万円)③ | 該当市のみ | - | - | - | 330,000×2=660,000 |
| 賦課基準額④ | ①−②−③ | 4,570,000 | 4,570,000 | 4,570,000 | 3,910,000 |
| 【医療分】 | |||||
| 所得割 | ④×所得割率 | 304,819(6.67%) | 399,875(8.75%) | 443,747(9.71%) | 331,959(8.49%) |
| 均等割 | 単価×加入者数 | 35,100×4=140,400 | 29,170×4=116,680 | 20,040×4=80,160 | 40,060×4=160,240 |
| 平等割 | 世帯あたり定額 | - | 23,640 | 24,720 | - |
| 小計 | 上3行の合計 | 445,219 | 540,195 | 548,627 | 492,199 |
| 限度額 | - | 660,000 | 660,000 | 660,000 | 660,000 |
| 医療分保険料 | 小計と限度額の 少ない方 | 445,219 | 540,195 | 548,627 | 492,199 |
| 【後期高齢者 支援金分】 | |||||
| 所得割 | ④×所得割率 | 122,933(2.69%) | 117,906(2.58%) | 112,422(2.46%) | 104,006(2.66%) |
| 均等割 | 単価×加入者数 | 10,700×4=42,800 | 8,940×4=35,760 | 6,360×4=25,440 | 13,110×4=52,440 |
| 平等割 | 世帯あたり定額 | - | 7,250 | 7,680 | - |
| 小計 | 上3行の合計 | 165,733 | 160,916 | 145,542 | 156,446 |
| 限度額 | - | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
| 支援金分保険料 | 小計と限度額の 少ない方 | 165,733 | 160,916 | 145,542 | 156,446 |
| 【介護分】 (40〜64歳のみ) | |||||
| 所得割 | ④×所得割率 | 68,093(1.49%) | 101,911(2.23%) | 125,218(2.74%) | 109,871(2.81%) |
| 均等割 | 単価×対象人数 | 11,500×2=23,000 | 8,760×2=17,520 | 9,260×2=18,520 | 15,340×2=30,680 |
| 平等割 | 世帯あたり定額 | - | 5,620 | 4,540 | - |
| 小計 | 上3行の合計 | 91,093 | 125,051 | 148,278 | 140,551 |
| 限度額 | - | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 介護分保険料 | 小計と限度額の 少ない方 | 91,093 | 125,051 | 148,278 | 140,551 |
| 国民健康保険料 年額合計 | 医療+支援金+介護 | 702,045 | 826,162 | 842,447 | 789,196 |
6. 国民健康保険と税金の関係(誤解しやすい点)
- 国保の賦課基準額は「総所得金額等−基礎控除(多くは43万円)」が基本です。→ したがって、青色申告特別控除や経費で「所得金額」自体を下げることは国保にも効きますが、iDeCo・小規模企業共済・社会保険料控除などの所得控除や、ふるさと納税(税額控除)は、国保の賦課基準額には直接効きません。
- 支払った国保料は確定申告で「社会保険料控除」として全額所得控除の対象(税金は軽くなる)。
- 「税金を下げる施策」と「国保を下げる施策」は必ずしも同じではない点に注意。
7. 国民健康保険料(国保料)を抑えるための打ち手
- 正しい記帳で「所得」を適正化
必要経費の漏れをなくす、減価償却や家事按分を適正に──所得金額が下がれば国保も下がる。 - 青色申告特別控除の最大化(65万円)
複式簿記+期限内申告+e-Tax等の要件を満たして所得金額を直接圧縮。国保にも効く。 - 国保組合の加入可否を確認
加入できる業界なら、国保組合の保険料・付加給付が有利なことも。 - 失業軽減・未就学児の均等割半減・低所得軽減の活用
該当すれば申請で下がる。離職(特定受給資格者・特定理由離職者)は前年給与所得30%みなしが強力。 - (番外)引っ越し
自治体差は依然大きいが、家賃や生活コストも含め総合判断を。
8. 国民健康保険料の支払い・スケジュール運用のコツ
- 通常、6月〜翌年3月にかけて年額を分割納付(回数は自治体差)。
- 口座振替にして納め忘れや紛失リスクを低減。最近はコンビニ・ペイジー・スマホ決済対応の自治体も増えています。
9. 国民健康保険(国保)でよくある誤解(公的情報ベース)
- iDeCoや小規模企業共済を払えば国保も下がる → 誤り。国保の保険料の算定基礎は「総所得金額等 − 基礎控除(多くは43万円)」。ここには医療費控除・社会保険料控除・寄附金控除などの所得控除は反映されません。
- 国保にも扶養がある → 誤り。国保に扶養の制度はありません。加入者が増えると均等割(+自治体により平等割)が増えます。
- 前年が赤字・所得ゼロなら国保はゼロ → 誤り。均等割(+自治体により平等割)は所得に関係なくかかります。低所得軽減や未就学児半減などの対象かを確認。
- 任意継続と国保を自由に行き来できる → 誤り。任意継続は原則最長2年、中途喪失は限定事由のみ、再加入は不可。退職直後に任意継続 vs 国保を期限内に比較検討。
- 都道府県単位化で保険料は同じになった → 誤り。都道府県が標準保険料率を算定しますが、実際の保険料率は市区町村が決定。自治体差は残ります。お住まいの自治体の保険料率・上限・均等割・平等割等を必ず確認しましょう。
10. 国民健康保険のよくある質問
Q1. iDeCoの加入により国民健康保険料は下がりますか?
A1. 下がりません。iDeCoの掛金は小規模企業共済等掛金控除として所得税や住民税を下げる効果はありますが国民健康保険料の賦課基準額には関係ありません。
Q2. 青色申告特別控除(65万円)国民健康保険料に影響しますか?
A2. 影響します。青色申告特別控除は所得金額そのものを下げるため、国民健康保険料の賦課基準額も小さくなります。
Q3. 未就学児の均等割半減って?
A3. 6歳未満(未就学児)の均等割が半額になります。
11. 国民健康保険のまとめ
- フリーランスは国保+国民年金が基本。国保は世帯単位・扶養なし・自治体差大。
- 国保の計算は「賦課基準額(総所得金額等−基礎控除43万円)」をベースに、所得割・均等割・平等割の合算。
- 国保を下げるには「所得金額を下げる施策」(経費の適正化・青色65万円)と制度軽減の活用が中心。所得控除や税額控除は効かないことに注意。
- 正確な金額は必ず自治体ページで試算(上限・割・軽減・半減など設計が違うため)。
- 失業・未就学児・低所得世帯の軽減制度は要申請。見落としやすいのでチェック。
12. 関連内部リンク
💬 Threads(@daichi_tax)で「税と会計の小さな気づき」を短文で発信しています。
👉 https://www.threads.net/@daichi_tax
📘 noteでは読みやすい”3分要約記事”を更新中です。
👉 https://note.com/daichitax